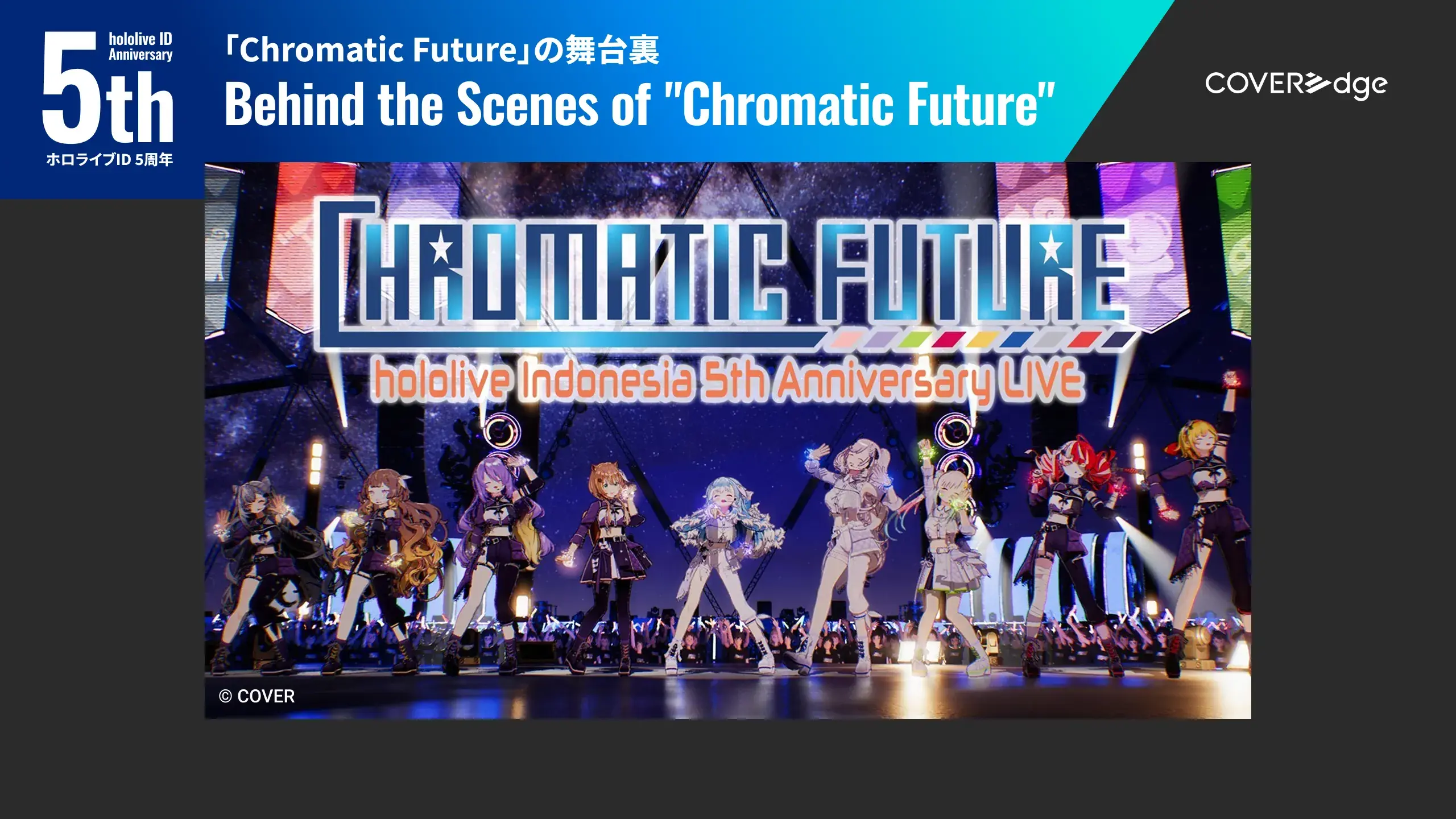いつもカバーならびにホロライブを応援いただいている皆さまこんにちは!
今回は、スタートしたばかりの「COVER USA」の責任者であるMさんにご登場いただき、「COVER USA」の事業活動と今後の目標や、北米におけるVTuber事情、グローバル化に向けて大切にしていることをお伺いしました。
2024年3月、カバー株式会社は「COVER USAを4月に設立し、7月から営業を開始する」と発表しました。おかげさまで多くのリスナーやファンの方からホロライブの北米進出にご注目いただいてます。
一方カバーでは、従来から海外事業に力を入れてきました。2023年9月には下記の記事を公開していますので、ぜひご覧ください。

カバー株式会社の海外事業本部。国内にとどまらない部署の環境や、その業務内容とは
今回は、海外展開をする際に重要な海外イベントについて注目し、それを取り仕切る海外イベントチームのRさん・Yさんに、また、海外事業本部全体のお話をMさんに聞いてきました。海外イベントをどのような想いで開催しているのか、本部として取り組んでいることや、今後の展望なども含めて、みなさんにお伝えできると嬉しいです。
北米支社・COVER USAがいよいよ始動! 従来の海外事業本部とどう違う?

―2024年7月から「COVER USA」が営業を開始、本日はお忙しいところありがとうございます!
こちらこそ、よろしくお願いします!
―早速ですが、Mさんのこれまでのカバーでのご経歴と現在の役職について教えてください。
韓国出身のMです。カバー株式会社に入社したのは2021年9月です。それまではアメリカやロシアのゲーム会社でプロダクトマネージャとパブリッシングプロデューサー職に就いており、韓国やシンガポールのオフィスで働いていました。
カバー株式会社は私にとって初めての日本企業で、当時営業本部内にあった海外営業チームのリーダーとして入社しました。そのころは、英語圏のタレントをマネジメントするチーム、インドネシア市場向けのチームなどさまざまな海外向けチームが役割ごとに各事業本部に所属しており、スムーズに連携しにくい状態だったのです。そこで海外向けチームをひとまとめにし、連携を密にしながら仕事を進められるようにということで、2022年に海外事業本部が立ち上がりました。
海外向けチームは私のような韓国人のほか、東南アジアや欧米出身者も多く在籍しており、日本語よりも英語でコミュニケーションしたほうがスムーズでした。そのため海外事業本部の現場では、英語でコミュニケーションをしてその成果や意見をトップと共有していこうということになり、私が海外事業本部の本部長となったのです。
現在は「COVER USA」でSales and Licensing Directorを担当しています。
―現在海外事業本部はどのような体制になっているのでしょうか?
海外事業本部には、タレントマネジメントや営業、PR、マーケティングイベントなどさまざまな部門がありました。本部もどんどん大きくなり、社内のスタジオチームなどタレントをサポートする社内シェアードサービス部門との連携も増えてきた一方、海外事業本部では社内にどのようなシェアードサービスやリソースがあるのか見えにくくなってきたのです。そこでやはり以前のような機能別にリソースを集中する形にしようということになり、現在は「海外事業本部」という部門はなくなりました。
それに、一言で「海外向け」とはいっても、アジア市場と欧米市場とはさまざまな面で異なります。そして、ヨーロッパや東南アジアとも全然違いますね。アジア圏は日本のカルチャーに関する受けがとても良いので事業拡張しやすいですし、時差もわずかなので日本本社からコントロールしやすい面もありますが、欧米だと時差や言語、マーケットスタンダードの違いなどの壁があります。
そこで「北米市場に本格展開するには、そうした壁を超えるために拠点が必要」という判断になりました。私も海外市場の拡張に向けてさらに貢献したかったので、今回「COVER USA」に赴任することになったのです。
COVER USAで進めている事業展開戦略

―Mさんは現在「COVER USA」でSales and Licensing Directorを担っているそうですが、どのような業務・ミッションを持っているのでしょうか。
「COVER USA」は少数精鋭で運営しており、全員が営業もしくはライセンシング業務を担当しています。私はその総括ということでSales and Licensing Directorとなっています。
現在「COVER USA」としては、北米のクライアントの方々とお話しし、現地の市場や北米のホロライブファンが何を求めているのか、どういう部分が実態と乖離しているのかを調査し、どのような分野なら拡張できるのかを考えつつ、営業・ライセンシング業務を進めています。今後事業が大きくなれば、北米でのタレントサポートなど業務範囲も増えたり業容も多様化してくると考えています。
さらに、この2つに加えて、私たちが検討している3つ目の取り組みは、よりユーザーフレンドリーな展開です。 コラボカフェやポップアップストアがその良い例です。 日本で働いていた頃は、日本以外の各地域でのコラボカフェやライブビューイングを実施するなど、ホロライブのファンが集まって楽しめるイベントに注力していました。 北米は地理的特性がアジア諸国と異なりますが、ファンが集まって「ファンコミュニティ」を楽しめる機会を開催できればと考えています。また、MD(マーチャンダイジング)などビジネス機能の拡大も目指しています。
―営業・ライセンシングに関する業務について詳しく教えてください。
営業、そして、ライセンシングに関連する業務は、大きく2つの領域に分かれています。
まず営業とは、タレントの影響力を背景にインフルエンサーマーケティングのような案件を開拓することが業務の1つです。クライアント企業の商品やサービスをプロモーションする案件配信をイメージするとわかりやすいかもしれません。
もう1つのライセンシングですが、カバー株式会社はタレントのマネジメントだけでなく「一緒にブランドを管理する」という特長があります。このブランドを利用してコラボ商品やグッズ制作などのコラボ事業を展開していくのがライセンシング事業です。
そして、上記に話したように、この2つの間に立つ「ユーザー体験型の事業」というのもあります。具体的にはコラボカフェですね。グッズ販売をしたりタレントをテーマにしたメニューを提供したりして、ファンの皆さんのコミュニティ活動をサポートしています。
―なぜその2つの事業に注力しているのでしょう?
北米ではまだVTuberを知らない方々も多いのです。そうしたなかでカバー株式会社やホロライブ、ひいてはタレントのブランド価値を高めるためには、まず対企業向けの施策が必要です。企業とのコラボレーションでVTuberを多くの人に知っていただくわけですね。そうすると、我々ができることも広がって、タレントの活動範囲を広げたり、やりたいことを実現できる確率が高まっていきます。
日本では、企業とのコラボレーションが私たちのブランド認知度向上に大きく貢献する一因となりました。今では、「ホロライブプロダクション」がサブカルチャーファンだけでなく、メインストリームのエンターテインメントとしても認知されています。これを北米でも再現できればと考えています。
そうした意味からも、「COVER USA」はカリフォルニアにオフィスを構えました。カリフォルニアは私たちと親和性の高いゲーム企業やエンタメ企業がたくさんありますし、日本企業のオフィスも多いので営業しやすいというメリットがあります。また、ホロライブのファン方のデモグラフィック(年齢、性別、居住地域、職業などの人口統計学的なデータ)によると、カリフォルニアを中心とする西海岸に集中していますし、大規模なアニメのイベントなども多数カリフォルニアで開催されているので、活動しやすいのです。
北米でVTuberカルチャーはどこまで浸透しているのか

―現地でのVTuberへの受け止め方はどのような感じでしょうか。
率直に言うと、こちらは日本と違ってVTuberという文化がそこまで浸透していません。日本のアニメについて知っている方は多いのですが、「アニメと似ているルック・アンド・フィールのカバーのブランドとコラボすることでどんなバリューがあるのか」をゼロベースからしっかり説明しないとなかなか理解していただけないのは事実です。
ただ、個人的な見解になりますが、最近1〜2年で状況は変わりつつあると感じています。というのは、この1〜2年の間で日本のアニメを見る若い世代が増えましたし、そういう兆しを認識してうまく自社事業のPRに取り入れている企業も出てくるようになりました。そのためVTuberを紹介しても、あからさまに「?」という顔をされることは少なくなったと思います。
もちろん、そうした変化が事業の成長や数字にどう結びついていくかは、これからの話になりますが。
―ゼロベースから大きくしていくことは大変だと思いますが、その点で苦労などはありますか。
大変ではありますが、北米でもコロナ禍でアニメを見る人がかなり増えましたし、可能性は大きいと思います。私も中高生の時に3年間アメリカに住んでいて、その時日本のアニメをよく見ていたのですが、当時はまだマイナーでした。その時に比べるとかなり状況は違います。もちろんサブカルチャーではあるのですが、以前よりはもっと広く消費されていると思います。『原神』のような日本ルックのゲームも人気ですしね。
ただ、アニメはやはり放映シーズン中が消費の中心なので、放映が終わると「もっと推したいのに!」というファンの期待に応えきれないという弱点があります。また韓国や台湾に比べると北米は本当に広いので、ファンが集まって推し活をするのが難しいという状況もあります。
逆にいえば「そこまでして集まるファン」の方々は、本当に熱い思いを持っている人たちなんです。「hololive Meet&Greet」では感動のあまり泣いてしまった方もいらっしゃいます。この7月にはつけ麺の『つじ田』とコラボして、当社の英語圏向けVTuberグループ「hololive English -Myth-」とのコラボメニューを提供したのですが、ファンの皆さんがずっと列を作って待ってくださっていて、つくづく「すごいな」と思いました。
以前海外事業本部で営業していた時にも、なかなか集まれなかったり、コツコツとグッズを集めるくらいしか消費できないなか、こうしたコラボコンテンツが持つ影響力に驚いたことがあります。いろんな事情で「推し活したくてもなかなか難しい」「同じファンと交流できない」という悩みを抱える北米のファンの方に向け、ライセンシングなどを通じてその思いをサポートしていきたいと思っています。
グローバル化に向けてカバー株式会社が取り組むべきこと
―Mさんがカバー株式会社に入社したきっかけを教えてください。
もともと日本のアニメが好きだったんですよね。ゲーム業界で9年仕事をしてきて、「もう少し違うことをしたい、これまでの知見をより広く深めたい」と思ったのがちょうどコロナの時期で、その時VTuberに興味を持ち始めました。私が好きな日本のアニメのようで、しかも「制作して終わり」ではなく、いろいろなコンテンツとして拡張していくという楽しさもあります。それで入社を決めました。
―外国籍の社員で、かつ北米での事業展開の中心を担っているMさんにお聞きしたいことがあります。これからカバー株式会社がグローバル展開していくに当たり、どういうことが必要だと思いますか。何かお感じになっている課題などがあれば併せてお聞かせください。
日本の会社なので当然ですが、外国籍社員として見ると「日本語コミュニケーションがメイン」というのは少し大変な部分もあります。外国籍社員に限らず、新しい人を採用する時にはその人の経験やスキルを見て採用すると思いますが、海外の社員が日本語のコミュニケーションに労力を割いて本来の実力を発揮できなくなっては本末転倒ですよね。それを防ぐには、現場で全員がスムーズにコミュニケーションを取りつつ、チームリーダーが社内の意思決定層と緊密に連携を取れるようになるのがこれからの重要な取り組みになると考えています。
―社員の英語力向上が鍵ですね。
いえ、むしろ私は「英語を話せればいい」という考えとは逆ですね。もちろんできるに越したことはないにせよ、英語のスキルが上がればグローバル化というわけではないと思います。
幸いなことに、いま社内には私のような韓国人を始め、アジアや欧米、北米などいろんな国や地域の方がいます。それぞれの国のカルチャーやトレンドにも通じていますし、能力も高い。言葉は違っても、そういう方々の知見やスキルを活かし、1つの目標に向かっていくことが大切なんだと思います。「みんなが協力して1つの目標を目指している」というリスペクトを持つことが一番大事なことだと考えています。
北米でVTuber市場を拡大するために
―これから北米の市場を拡大していくに当たり、どのような人と一緒に働いていきたいとお考えですか。
事業を拡張するには、私たちがアプローチしている領域の企業の方々とどうコネクションを作っていくかがポイントになります。そういうことを考えると、やはりターゲットとしている業界に精通している方であったり、また北米のカルチャーややり方をよく知っている方、現地の考え方を理解している方であるとなお良いと考えています。
これは北米市場に限らず、どの国や地域に進出していく時でも同じだと思います。
―今後の目標をお聞かせください。
北米でのプレゼンスを高めることが私の役割です。そのためにも北米の大きな企業とのコラボやインフルエンサーマーケティングを進め、当社のタレントやブランド価値向上につなげていきたいと思っています。そして、タレントたちを北米での配信やゲームコミュニティに繋いだり、北米で「ホロライブプロダクションの推し活」がもっと楽しめるものにできる機会をつくれたら嬉しく思います。