
今回登場いただくのは、ライセンス事業本部 ライセンス部の部長を務める尾関優さんです。2020年に入社した尾関さんは、カバーのライセンス事業の立ち上げを担い、現在に至るまで、さまざまな企業とのコラボレーション企画を推進・実現しています。
ライセンスにまつわる業務は、VTuberのキャラクターや商標等の使用許諾と監修だけではありません。ホロライブプロダクション所属タレントの活動を後押しし、新たな価値や魅力をファンにしっかり届けられるように企画を精査する。また、ブランドを守るべく商品のクオリティを担保したり、市場や業界にインパクトを残すようなアイディアを出したりと、多様な角度からアプローチが必要です。
そんなライセンス事業について、尾関さんは「カバーだからこそ、挑戦できる可能性は広く、やりがいがある」と断言します。今回はその挑戦と可能性について詳しく伺いました。
モノとコトの体験を通じ、プロダクションの新たな価値を創り届ける
―すごい! フィギュアやスニーカー、デニムジャケットまで、さまざまなグッズがありますね。どれも欲しくなってしまいます。
ありがとうございます!ライセンス事業では豊富な種類のグッズの企画・制作に関わっています。

―こうしたグッズ制作の一役を担うライセンス事業本部の業務について教えていただけますか?
ライセンス事業本部の主たる業務内容は、ホロライブプロダクションにおけるライセンスビジネスの運用と推進です。少し噛み砕いてお伝えすると、ライセンスビジネスは「モノ施策」と「コト施策」の2つに分かれます。
「モノ施策」とは、こちら(写真・上)にあるようなフィギュアやアパレル商品の企画制作のことです。カバーのマーチャンダイジングにおいては、自社商品の制作を担う商品企画本部もあり、お互いに連携しながらホロライブプロダクション全体のグッズ企画を推進しています。
「コト施策」とは、人が集まる場所での体験価値の創出ですね。商業施設とのコラボレーションやアニメグッズ販売店でのフェア、コンビニエンスストアとの共同キャンペーン、コラボカフェの実施などが主な事例です。また、ゲームセンターのクレーンゲームのプライズ(景品)なども体験価値の1つと捉えています。
―施策の実現に向けて、どのように企画を進めていくのでしょうか?
例えば「タレントの○○さんとコラボしたい」というお話を企業の方からいただいた場合、私たちは案件に対して「このブランドでの展開は、タレントさんの価値向上につながるのではないか」などを多面的に検討し、タレントさん本人の意思を確認しながら、デザインや制作など具体的なプロセスを進めていきます。
また、逆のパターンもありますね。「タレントの○○さんは夏にこういう施策があるから、時期を合わせてコラボカフェを展開できないか」という社内の意見をふまえて、私たちが提案に出向くこともありますね。
企業とのコラボを進める「ライセンス」、クオリティの担保と制作窓口を担う「ブランド管理」の両輪体制

―次に、ライセンス事業本部の体制を教えてください。
ライセンス事業本部は、「ライセンス部」と「ブランド管理部」で構成されます。私が担当しているライセンス部は、ライセンサー※1として事業を推進しています。ブランド管理部は、制作されたグッズなどのデザインや使用方法の監修をはじめ、イラストレーターさんやクリエイターさんへの発注管理を担っています。本部全体では約30名のスタッフが所属し、そのうちライセンス部は11名が業務にあたっています。
※1:自らが保有するIP等を契約に基づき他者へ提供する者
―現在は約30名が在籍する事業本部ですが、尾関さんは立ち上げから在籍していると聞きます。
そうですね、2020年に入社した当初、ライセンス事業の立ち上げを私が担当しました。当時ライセンス事業はマーケティング部門の傘下にあったので、売上というよりは「マスに向けて認知を広げること」「応援してくださるファンの方に、ホロライブプロダクションの成長を実感していただくこと」という目線で、企業との取り組みを増やしていくことを目標にしていました。そして、3〜5年先という将来を見据えたスパンでどういう展開ができるかイメージを描き、優先順位を付けて戦略交渉を組んでいったのです。
商材の中には、フィギュアのように企画から商品が完成するまでに、長いと2〜3年かかるものもあります。そのため、早めにアクションを取る必要がありました。とはいえチームの立ち上げ序盤は動けるメンバーが限られていました。
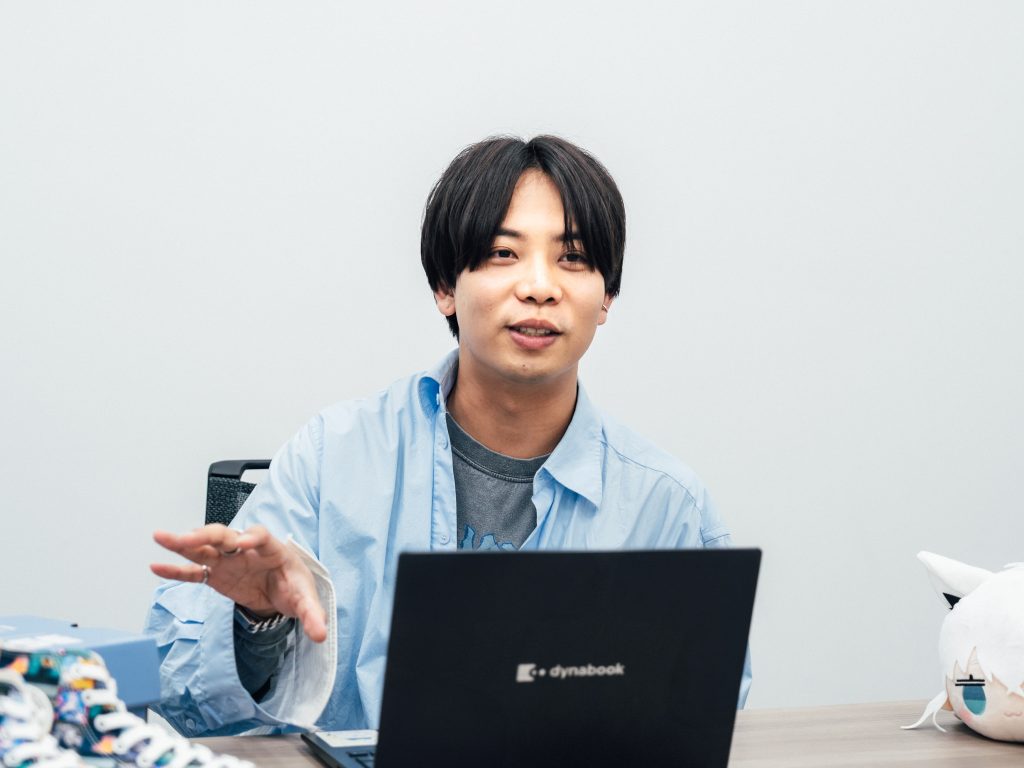
そこでまずは、マーケティング的に効果が高い商材から順番に商品化の許諾を出していくようにしました。そうすると、商品のクオリティを担保するために制作物の監修も必要になってきます。立ち上げ当初は、タレントさん自身に一つひとつ細かく監修していただき、「この部分が足りていません」と指摘いただくこともありました。チームメンバーが増えて、組織として監修チームを編成できるようになった今においては、タレントさんへ依頼する作業は削減できるようになりましたね。
またクリエイターさんへの発注窓口など、付随する業務が増えるなかで、さまざまな経験を持ったメンバーを迎え入れ、現在のような体制に至ったという次第です。
―尾関さんが現在担当しているライセンス部の特長や強みにはどのようなものがありますか?
組織効力感の高さが顕著だなと感じていて、そこは誇れる部分だと思っています。ひとりで企画を進めていると「タレントさんはこの企画をどう思うだろうか」と考えあぐねたり、シンプルに「この商品はいいものなのかな?」「この進行で大丈夫?」と不安になりがちでしたが、今はチームとして「この壁は乗り越えられそうだね」「このまま行ける、上手くいく!」というマインドを感じるようになりました。
これはほかのどの部門にも負けないところで、特にここ1年くらいはチーム力がレベルアップしてるという実感があります!
タレントの活躍をバックアップ、ファンの期待に応えるために
―業務内容を詳しく伺いたいのですが、何か商品の事例をお話いただけますか?
こちらのスニーカーは、以前コンバースジャパンさんとのお取り組みで、星街すいせいさんとのコラボレーションを実現した商品です。『ALL STAR』は「CONVERSE」を代表するアイコンですし、星街すいせいさん本人もコラボレーションに賛同してくださったので、企画が進んでいきました。

このコラボ企画では「一般ユーザーやファッション愛好家に向けて“かっこいい”と思ってもらえるものを作る」ということを目的にしていました。というのも、星街すいせいさんご自身が新たな活躍フェーズへ進み、より幅広いファンの方々に向けてより高い価値を提供していく、まさにそんな渦中にいらっしゃったからです。私たちの役割は、タレントさんのさらなる活躍・成長をバックアップすること。そこでコンバースジャパンさんとともに企画の精査を進め、関係各所と丁寧に連絡を取りながら、制作に向けて全体の調整を行いました。
発売は今年2月、全国の「ABC-MART」店舗および「ABC-MART」公式オンラインストアでスタートしたのですが、店舗ではイベントが開催され、インフルエンサーの方々を招いて実際にシューズを履いていただく場面もあり、行列ができるほど人が集まり、非常に盛り上がりました。ファッション業界にもVTuberの影響力を印象づけられたと自負していますし、とても印象深かった施策の1つです。
―その他にも、スニーカーとは異なる観点でご紹介いただける事例はありますか?
ゲームセンターのプライズ(景品)の制作では「より高い付加価値の実現に向けて、どの企業さんと一緒に取り組むことが最適か」という点を重視していました。
ありがたいことに、現在はホロライブプロダクションのタレントたちの活躍により、様々な企業から「商品化させて欲しい」とお声がけいただいています。だからこそライセンス部は「より高い価値の実現」という観点で、コラボレーション相手を検討させていただく必要があるわけです。

こちらはプライズメーカーとコラボレーションして制作しました。このプライズについては、商品単体で精査するのではなく「クレーンゲームの筐体にこの商品が積まれている時、お客様の目にどう映るか」という点を想像しながら試行錯誤を重ねました。こちらのメーカーさんは「商品軸でもホロライブプロダクションを一緒に育てていこう」という思いでカバーに寄り添ってくださり、お顔のデザインだけで数十パターンものアイディアをいただいたほどです。最終的にはいただいたデザイン案をあらゆる角度から吟味し、デザインをフォーマット化して、毎月新しいプライズを展開していくことにしました。
そうすることで、ファンの方々は「来月になれば自分の推しが登場する」と期待も高まるでしょうし、クレーンゲームでこの景品が積まれている姿を見て「かわいい!」と思い、新たにファンになる方もいるでしょう。このような展開によってタレントさんにも貢献できますし、ホロライブプロダクションの価値向上にもつながると考えています。
―グッズというと、フィギュアも思い浮かびます。フィギュアの場合、どのような点が重要なのでしょうか。
実はフィギュア制作には、特有の難しさがあるんです。フィギュアの制作プロセスには造形師さんや色を付けるフィニッシャーさんなど、多様なプロの方が携わるうえ、流通もカスタマーサポートも独自の方法があるので、それらを熟知して制作に当たらなければなりません。
フィギュア化されるIPは多種多様ですが、制作のレーンが変わるだけでクオリティが変わることもあります。完成品イメージと実際の商品の間に大きくクオリティの差があり、ご購入されたファンの方ががっかりしてしまうような事例を他作品にて過去目にすることもありました。
ファンの皆様の期待にこたえるクオリティで制作するために、私たちライセンサーは、フィギュアにとってベストなレーンでの制作が実現できるよう、しっかりとしたリレーション・コミュニケーションを取ることと、商品監修を行うことが求められます。

チャレンジしやすい業務だからこそ、必要なこと
―ライセンス事業を担うに当たり、必要なスキルや経験はありますか?
そもそもライセンスビジネスについて、私はそこまで難しいビジネスだと考えていません。私たち自身はフィギュアや服の作り方を“何となく”知っているだけで、プロではありません。しかしライセンサーとして商品化を許諾すれば、その道のプロに商品を作っていただくことが可能です。端的に言えば「許諾すれば商品はできる」のです。
だからこそ、「どういう企業さんと進めていくのか」「提案いただくサンプルと同等のクオリティで本当に制作いただけるのか」をジャッジできる審美眼は必要です。ジャッジを誤ると、前述のとおり商品のクオリティを担保できず、タレントさんのブランドを傷つけてしまうリスクがあるからです。
また、今何が流行っていて、競合を含めた他社がどういう展開をしているのかなどを知っておくことも必要です。例えば、電車の中で吊り広告を見たり、コンビニに行ったついでにキャンペーンやタイアップ商品をチェックしたり、秋葉原の街中の看板に何が出ているのか確認したりしながら、「ホロライブプロダクションのタレントさんならこんな企画ができるかもしれない」と自分のなかにインプットしておく。その積み重ねが、案件と直面したときに、引き出しの質と量になります。
でも、本当にそれだけで、基本的に特別なことをしなくても社会人としての素養やコミュニケーション能力があり、ホロライブプロダクションを含めエンタメが大好きという方であれば、チャレンジできるビジネスだと思いますね。

―ライセンス事業ならではのやりがいを教えてください。
何と言っても、あらゆる可能性があることでしょうか。「タレントさんの活動に加勢して、ファンの方に新しい価値を届けたい」という熱意と企画力があれば、新しいことに挑戦できる環境があります。
また、この仕事をしていて個人的に嬉しかったこともたくさんありましたね。音楽ライブやイベントで、私たちが企画したTシャツやパーカーを着ているファンの方を見ると「気に入ってくれているんだ」と嬉しくなって、声をかけたくなってしまいます(笑)。
企画商品の情報解禁時に、SNSでポジティブな意見が多いとやりがいを感じますし、「運営、ちゃんとわかってるな」というコメントを見ると、「ありがとうございます!」という気持ちとともに業務へのモチベーションが上がりますね!「〇〇さん、いい仕事してる」とコラボした企業に言及している投稿があれば一層嬉しくなります。
ファンの方だけでなく、タレントさんが自分のグッズを配信で紹介して「自分も気に入っているんだよね」と言ってくれるのもやりがいの1つです。こういうやり取りがあるのも、VTuberが持つユニークさだと思いますね!
パートナー企業との信頼関係を礎に、グローバルな価値拡大を目指す
―そもそもですが、尾関さんがカバーに入社したきっかけは何だったのでしょうか?
私はもともと新卒で総合エンタメ企業に入社して、音楽事業やマネジメントなど、多様な業務を担当した後、株式会社Tokyo Otaku Modeというエンタメ企業に転職しました。そこで2次元コンテンツに関わることになり、バイヤー業務や、ライセンシーとして取引する業務を経験したのです。今とちょうど逆の立場ですね。
株式会社Tokyo Otaku Modeを退職し、転職活動をしていた時に知人からカバーを紹介してもらいました。当時、別の会社に内定が決まっていたのですが、「谷郷さんはとても面白い人なので、ぜひ会うべきだ」と強く勧められ、お会いすることになったんです。当時は入社する気はなかったですし、VTuberという文化に対しても懐疑的だったので、いま振り返るとかなり失礼な態度だったと思います。
谷郷さんがお話の中で、ホロライブプロダクションへの強い思いや、目指している長期的なビジョンを説明してくださり、谷郷さん自身が世界で一番ホロライブプロダクションやタレントさんの可能性を信じていること、その可能性を広げるために必要なことを詳しく語ってくださいました。その話を聞いて、私も「貢献できるかもしれない、一緒にチャレンジしたい」と思ったのが入社のきっかけでした。
当時谷郷さんが探していたのは、商品の企画開発ができる人材でした。しかし「尾関さん、お話するのが得意だし多分できると思うので、ライセンスをやってもらえますか?」と相談され、そこでライセンス事業の立ち上げを任せていただくことになりましたね。
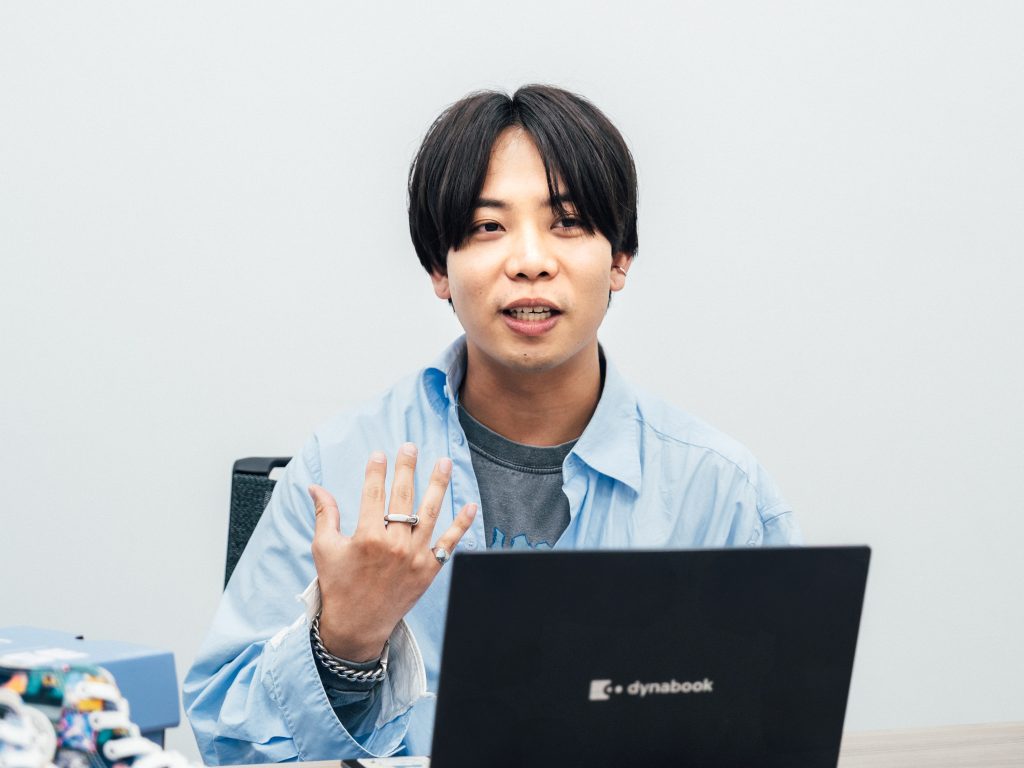
―仕事をするうえで大切にしていることは?
私はライセンシー側を経験しているので、許諾を出す側のライセンサーと、受ける側のライセンシーの関係性や両方の気持ちや考え、意図が理解できます。そのうえで、私がベンチマークにしているのは、以前ライセンシー時代に取引があった出版社の担当者の方です。その方は版元という立場でライセンシーと同じ目線で共にスクラムを組み、「一緒に作っていきましょう」というスタンスで接してくれました。
この世界は、つまるところ人と人の関係で成り立っているので、「ファンの方に価値の高い、いいものを届けていきましょう」と対等に話し合えることが何よりも大切なんです。このエピソードはチームメンバーに対して「最も重要なこと」と伝えていますし、私自身の一番の経験になっていると思います。
―今後、ライセンス部が挑戦したいことを教えてください。
タレントさんは一人ひとりブランディングも違えば、方向性も趣味嗜好も異なります。なので私たちは、一人ひとりのタレントさんにしっかりフォーカスし、その価値をライセンス事業で高めていきたいと考えています。
それに、日本発のコンテンツでこれだけ世界に届いているコンテンツは類を見ないと思います。何百億円も投資しても世界に届かなかったIPはたくさんありますが、ホロライブプロダクションは言語の壁を越え、世界各国で認知していただいている環境があります。それは本当に恵まれた環境だと思っていますが、決して「届いて当然」と驕ってもいません。
この「当たり前ではない」という点を大事にしていきながら、世界中に対してその価値提供をしていくことが会社としては必要ですし、それがカバーの掲げている「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」というミッションにつながると思います。
ライセンス部は、そんなグローバルなチャレンジをしていくためにも、引き続き事業を展開していきますし、そこから今後何が生まれてくるのか私自身も楽しみにしています。

―ありがとうございます。最後に「等身大のカバーを一言で表すとしたら」、尾関さんはどのように表現しますか?
この回答、実は事前に色々と考えてみたのですが、ピンとくるものがなかったんです(笑)。
振り返ってみると、私自身5年間カバーで仕事をしてきたのですが「今は第二創業期のような立ち位置」「ここからだな」という感覚があるだけです。
というのは、会社が上場し、成長曲線もちょうど踊り場にきている今現在、本当に「ここから何をどう展開するのか」が重要だと感じているからですね。
これまでは、タレントさんの力をドライバーに会社が成長してきたと思っています。しかしここからは、社員自身もしっかりと戦略に基づいて会社を牽引していく時期に来ているのかもしれません。今のカバーは5年前と異なり、専門分野のプロフェッショナルが集まっています。まさにここから、新しいカバーが生まれるでしょう。
ライセンス事業本部の取り組み事例として、こちらの記事も合わせてご覧ください。
本記事に関連する採用情報は下記よりご確認ください。









