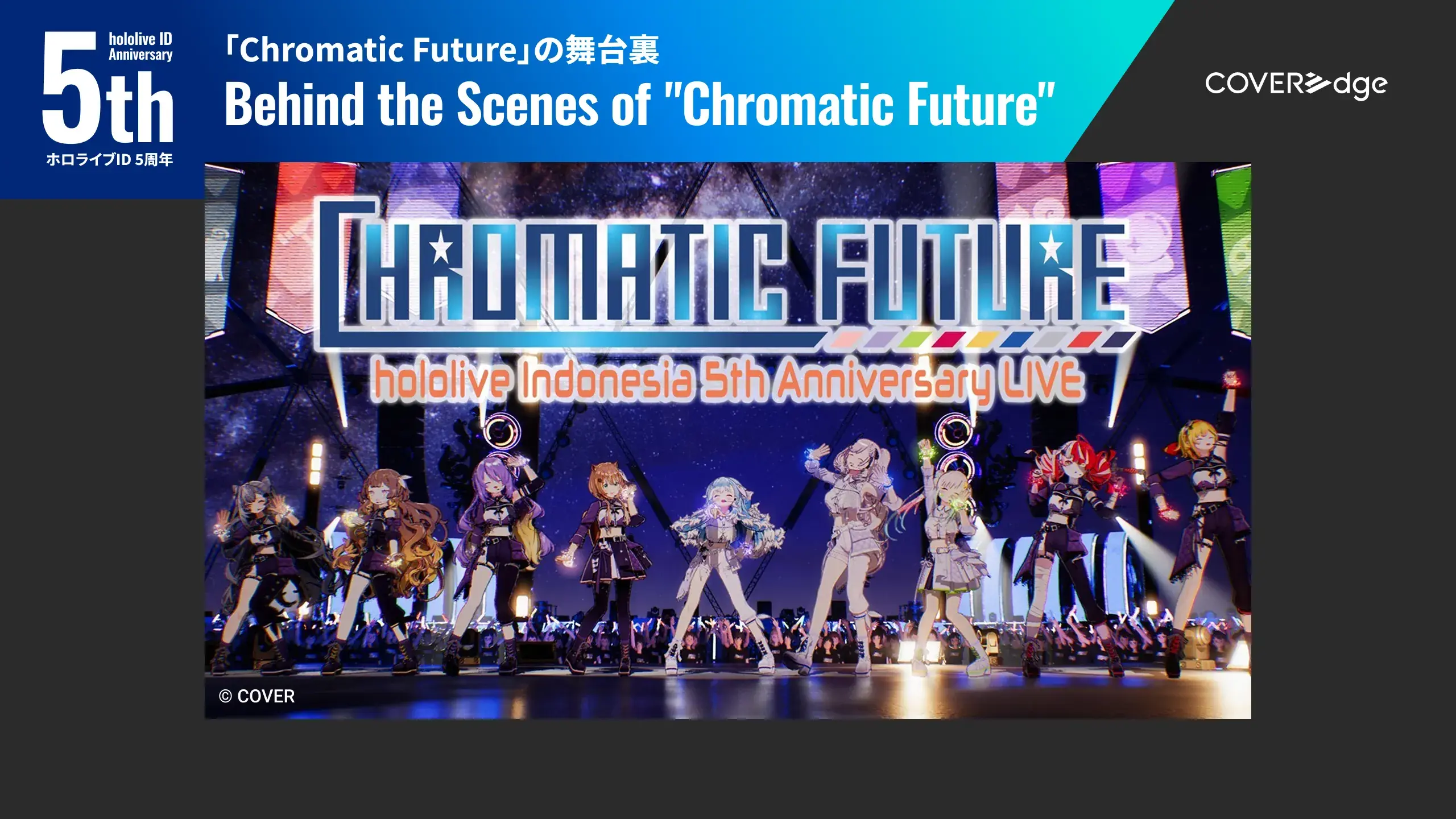VTuber事業「ホロライブプロダクション」やメタバース事業「ホロアース」を世界に展開するカバー株式会社。2024年5月に新設された海外事業開発室は、世界市場を開拓し、VTuberの存在感を高めるための重要な役割を担っています。その指揮を執るのが、エンターテインメント業界で豊富な経験を持つ鈴木萌子室長です。ハリウッド映画のプロデュースから日本作品の海外展開まで、数々のプロジェクトを手掛けてきた鈴木室長に、カバーの世界戦略について、前後編にわたり、詳しく伺いました。
前編では鈴木さんの今までのキャリアについて、そして、後編では現在取り組んでいる海外事業の業務内容や今後の展開について迫ります。
「グローバルとエンターテインメント、2つの原点が導いた道」ハリウッド映画プロデューサーから海外事業開発室長として新たな挑戦へ
―現在の海外事業開発室の業務内容や役割について教えてください。
海外事業の責任者として海外展開に向けた戦略立案や施策遂行をリードしていく役割を担っています。現在13名が部署に所属していて、年齢構成としては20代後半から30代前半が中心です。メンバーの専門分野は様々ですが、「日本のビジネスを海外展開したい」という強い意欲があるメンバーが集まっています。また、日本のアニメ文化へ深い愛着を持っていることも特徴ですね。それぞれのチームが専門性を持ちながら、全体としてグローバル展開を推進していく体制づくりを心がけています。
―2024年5月にカバーに入社され、海外事業開発室の立ち上げを行った鈴木さんですが、これまでのキャリアについて教えていただけますか?
新卒でアクセンチュア株式会社に入社し、戦略コンサルタントとして製造流通業種のクライアントを担当していました。日本のビジネスを世界展開していくプロジェクトに携わることが多く、次第に、元々興味のあったエンターテインメント分野で海外展開戦略を練る仕事をしたいと思うようになりました。
そして経済産業省が推進する「クールジャパン戦略」を基盤とした会社に転職し、ビジネスディベロップメントマネージャーとして、日本作品のハリウッド映画化事業に携わり、日本の人気作品の映画化プロジェクトを手掛けました。この過程で培ったノウハウや人脈は、その後のキャリアの大きな財産となっています。その後、株式会社アカツキ(以下、アカツキ)に入社し、COO室室長およびAkatsuki Entertainment USA取締役として、ハリウッド映画化のプロデュースや、イマーシブエンターテインメント※事業の立ち上げ、新規ゲーム開発など、ライブエンターテインメントからゲームまで幅広い分野で海外展開を推進してきました。
その後、アカツキの事業再編に伴い、映画事業を継承する形で株式会社AMMO(以下、AMMO)を設立し、有名漫画コンテンツのハリウッド映画化や多数の受賞歴があるミステリー小説のアメリカでの書籍出版など、日本作品の権利取得からファイナンス、制作会社の選定、配給まで一貫して手掛けてきました。日本のエンターテインメント業界は海外展開の経験値が比較的浅い側面がありましたが、その分野で新しい可能性を追求したいという思いが常にありました。海外市場とエンターテインメントの掛け合わせという軸は、私のキャリアを通じて一貫して持ち続けてきたテーマです。
※イマーシブエンターテインメントとは、ヘッドマウントディスプレーを用いるVRコンテンツや、空間全体が舞台となり観客も物語の登場人物の一員となるなど、没入感を重視した“体験型エンターテインメント”を指します。

―海外市場とエンターテインメントへの想いの原点となったきっかけはありますか?
グローバルな視点は、家族から受けた影響が大きいですね。外資系企業に勤めていた父の影響で、帰国子女ではないものの、幼い頃から「世界は日常的に触れている範囲だけではない」ということを自然と学びました。
エンターテインメントへの情熱は大学時代の演劇活動が原点です。大会でグランプリを獲得した経験は、今でも私の背骨となっています。エンターテインメントの価値は、時として目に見えづらく、感動するかどうかは紙一重です。しかし、この世界で活躍する人々は、単なるロジックだけではなく、自分の命を懸けて作品と向き合っています。そうした真摯な姿勢に深く感銘を受け、エンターテインメントに関わる仕事がしたいという思いが芽生えました。
こうして振り返ると、グローバルな視野とエンターテインメントへの情熱は、私のキャリアの両輪として、常に相互に影響し合いながら発展してきたように思います。
「クリエイティブを最後の1秒まで信じ抜く」映画プロデューサーとしての経験が導いた、VTuber業界への挑戦
―海外市場に向けて映画制作から配給までを行う事業を手掛けてきた鈴木さんが、VTuber業界に注目されたのはどういった経緯だったのでしょうか?
AMMOで二本の映画を作り終えた頃、これまで映画製作など、作品単位での成果は出せてきたと実感していましたが、それが業界や産業を変えるようなインパクトのある成果に繋がったかと問われると、個別のプロジェクトで完結してしまっていたという思いが強くありました。私自身40代を目前に控え、次の10年が自分のキャリアの分岐点になるだろうと考えていました。それまでは面白そうな経験やチャレンジに惹かれる傾向がありましたが、この先のキャリアを広げていくには、本当の意味で「大きな実績を作る」ことが必要だと痛感していました。
加えて、私のキャリアの中で「海外展開」は外せないキーワードでした。そこで、海外展開で本当に勝てる場所を探し、「その勝負に本気でこだわっている会社を探してる」と周囲に相談すると「それならVTuberの会社だ」と言われることが多く、そこからVTuber業界について勉強を始めました。VTuberについて、当時はほとんど知らず、ビジネスモデルの核心部分も、エンターテインメント業界でここまで新しい領域を切り開いている状況も把握していませんでした。最初は「実写のストリーマーのアニメ版で、より小規模なもの」という印象を持っていましたが、実際に学んでいくと、VTuberは実写配信より規模は小さいものの、ビジネスモデルが全く異なり、むしろビジネスとしてのスコープや可能性は遥かに広いことがわかってきました。VTuber関連業界の会社全体が本気で海外展開や新規市場開拓に取り組む姿勢を感じ、これは業界やマーケットが確実に伸びている証だと思いました。
ーそこからカバーへ入社を決めた決め手はなんだったのでしょうか?
最大の決め手は「クリエイティブへのリスペクトの深さ」でした。エンターテインメントの魅力は必ずしもロジックだけでは説明できないもので、単に商材としてエンタメを扱う会社は本質的ではないと私は考えています。その点、カバーには本物感がありました。「どうやって儲けるか」も確かに大切ですが、その前提としてエンタメや自社コンテンツの本質的な魅力を語る、谷郷さんや面接でお話ししたカバーの方々に本心を感じました。
加えて、すでに世界中にファンベースがあるというのも大きな決め手でした。私はこれまで様々な作品に関わってきましたが、「ホロライブプロダクション」のように既に世界で強固なファンベースが確立されているケースは非常に珍しいです。日本では有名な漫画でも、世界的なファンベースの構築には時間がかかります。カバーのコンテンツは既に世界中で視聴されており、ファンの方々がタレントのちょっとした仕草や言動に魅了され、そうした感動の瞬間が一つ一つビーズのように積み重なって大きなファンベースを築いています。この貴重な状態を、鮮度が落ちないうちにしっかりと開花させていきたい、という思いを強く持ち、入社を決めました。

ー鈴木さん自身が大切にしていた軸と、カバーの持っているポテンシャルや視座がパズルのピースのようにハマったのですね。ハリウッド映画をプロデュースするという経験は、今どのようにカバーで活きていますか?
映画作品の選定では必ず「この作品にしかない魅力があるか」を重視していました。日本の作品を映画化する際は、その実現可能性も重要な判断材料です。例えば『ALWAYS 三丁目の夕日』のようなハイコンテキストな作品は、翻訳の過程で魅力が失われてしまう可能性が高い。一方、『リング』シリーズのようなホラー作品は、設定を変更しても本質的な魅力を保ちやすい特徴があります。そういった専門的な視点で見極めていきつつも、最後に最も重要なのは、その作品の魅力をプロデューサーである自分が信じられるかどうかです。作品の商業的な成功よりも、この点が最も重要だと思っています。なぜなら、プロデューサーの「信じる」という思いが、監督に伝わり、監督から作家へ、そして最終的に観客へと連鎖していくからです。映画の成功は開けてみるまでわかりません。だからこそ、クリエイティブの最後の1秒まで、自分が本当に信じられる作品かどうかが決定的に重要でした。
この「信じる」という姿勢は、今のカバーでの仕事にも深く通じています。VTuberはIPとしての顔を持ちながら、同時にタレントとしての側面も持つ、という特殊性があります。彼&彼女たちの魅力を心から信じ、その可能性を信じてビジネスを展開していく。この思考パターンは、私が映画製作で培ってきた経験とも非常にフィットしていると感じています。
後編では、現在取り組んでいる海外事業の業務内容や今後の展開についてお話しいただきます!
海外事業開発の採用情報は下記をご確認ください
【海外事業開発(トレーディングカードゲーム)】世界を熱狂させるTCGを創る!グローバル展開を牽引する事業開発担当募集
【海外事業開発(リーダー候補)】日本発グローバル事業の成長を共に実現しませんか?