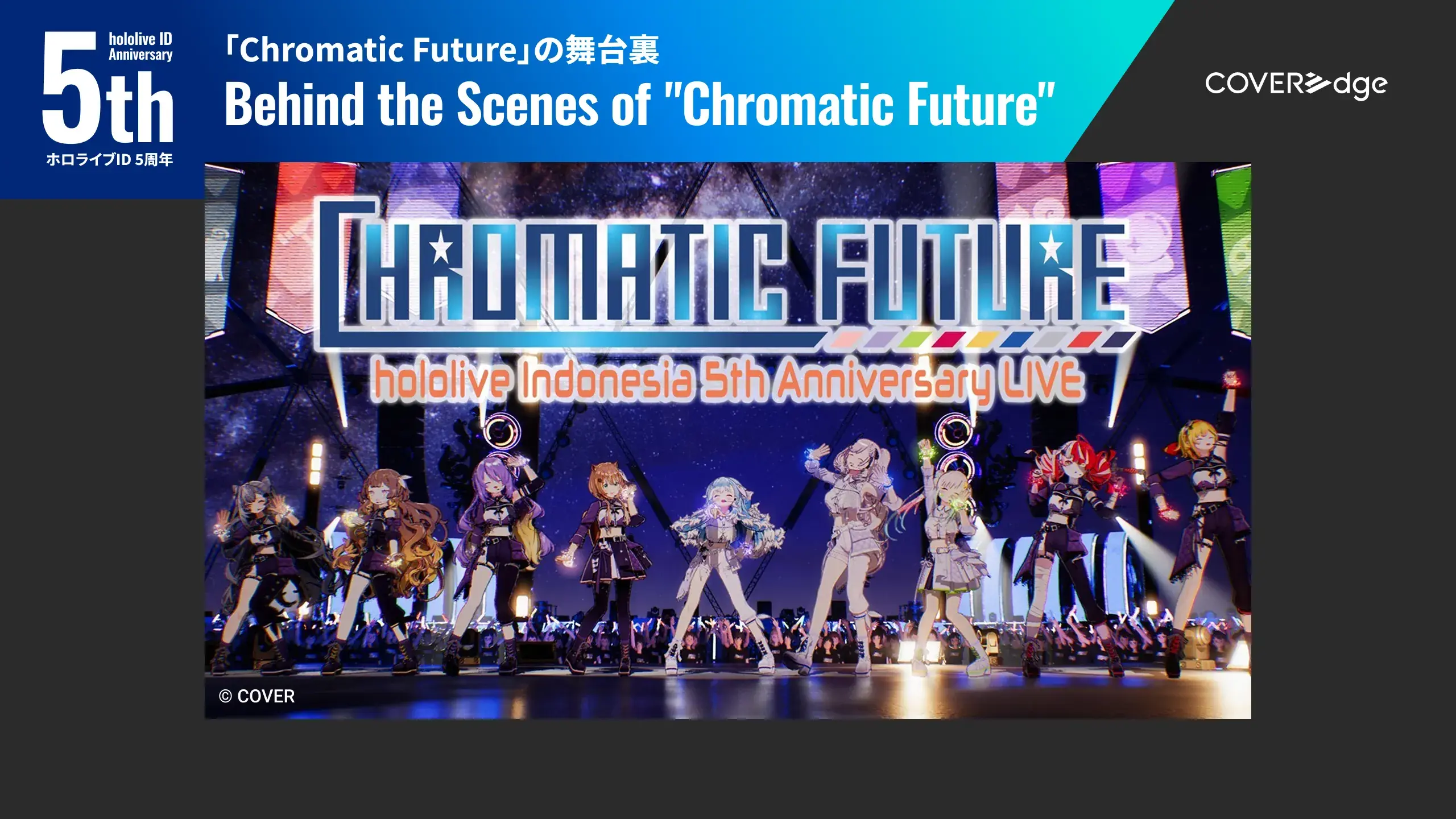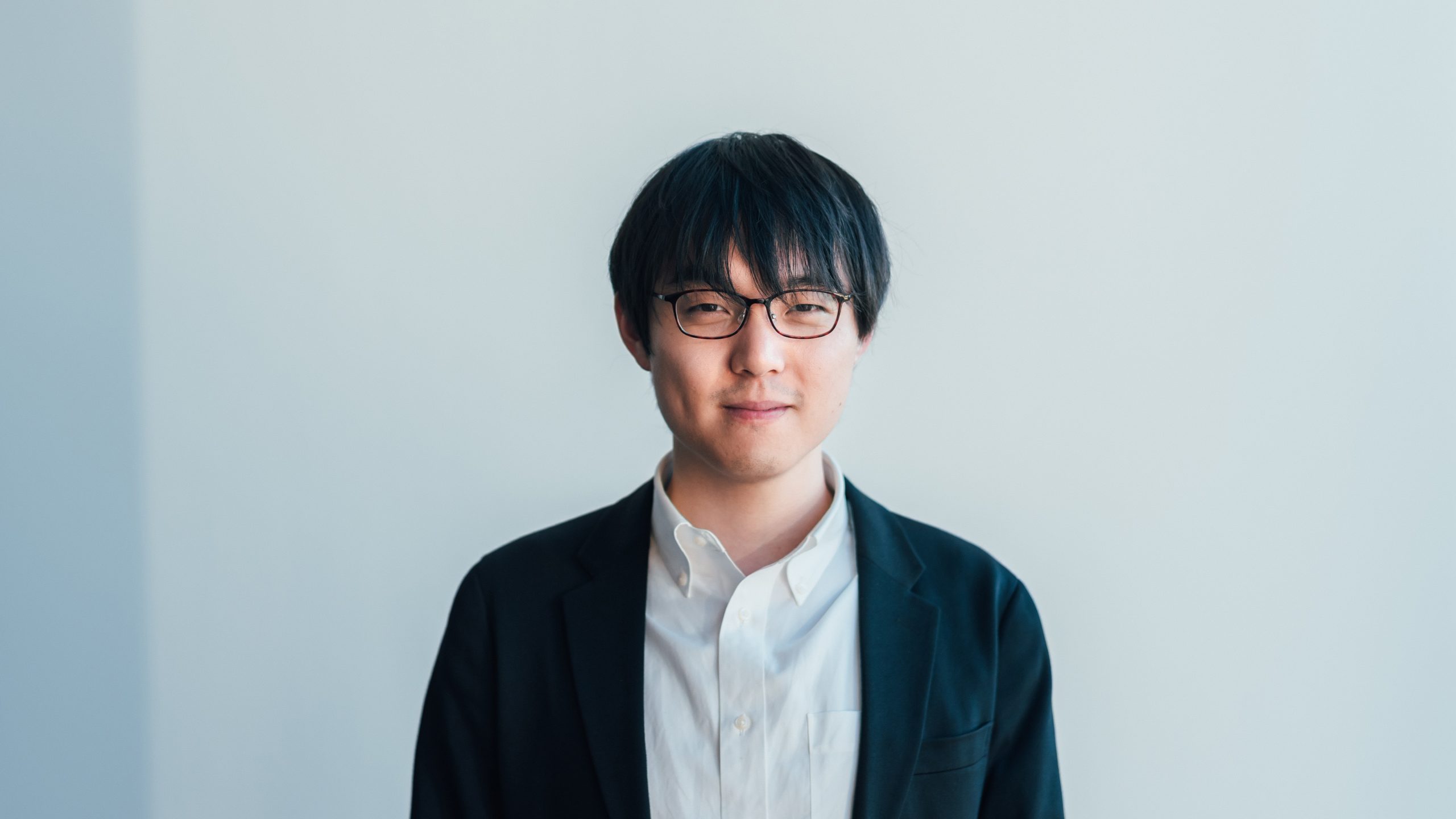
VTuber事業「ホロライブプロダクション」を展開するカバー株式会社は、総合エンターテインメント企業を目指しています。成長の裏側で、タレントと社員双方の活動を支える管理部門を統括しているのが、執行役員 人事/法務知財・危機管理本部長の加藤卓さんです。加藤さんは2020年にカバーに入社し、その後執行役員に就任。VTuber事業を基軸としたカバーならではの、独自の管理体制を築いてきました。持続可能な組織づくりを目指す取り組みについて、詳しく伺いました。
VTuberやタレントを支える、独自の管理体制の構築
―2020年に管理本部長兼人事本部長として入社されています。これまでのキャリアと、現在の業務内容について教えてください。
新卒で日本郵政に入社したのち、公認会計士の資格を取得して監査法人トーマツに勤務しました。その後、医療系ベンチャーで取締役COOを務め、転職エージェントを通じて2020年にカバーへ入社し、現在5年目を迎えています。
今振り返ってみると大企業とベンチャー企業の両方で得られた実務経験と、監査法人時代に様々な会社のガバナンス体制に触れることが出来たため、色んな引き出しを持つことが出来たように感じます。
こうした知見はカバーにおいても様々な課題に柔軟に対応するうえで役に立ち、数十人~数百人規模に組織・事業が急拡大していく中でも振り落とされずにいられたのだと思います。
入社当初は人事・経理部門の業務からスタートし、契約書チェックなどの法務業務も担当するようになり、徐々に総務機能なども整備してきました。現在は管理本部、人事本部、法務知財・危機管理本部と専門分野別に区分した体制となっています。
特徴的なのは、タレントサポートの機能です。タレントマネジメント本部がタレントの本業に伴走する一方で、私たちはタレントマネジメント本部ではすくいきれない手続き面などのサポートを担当しています。このように社員とタレント、双方の管理業務を行っている点は、当社のバックオフィスの特徴ですね。
―タレントが安心して活動できる環境づくりやタレント事業特有のリスク管理について、取り組みを教えてください。
タレントサポートの取り組みは2020年頃から段階的に整備を進めてきました。会社設立のサポートや税理士の紹介など、事業面でのサポートを徐々に拡充させ、昨年からは健康診断制度も導入しています。活動が忙しくなる中で体調管理に悩むタレントの方々の声を聞き、定期的な健康チェックの機会を設けることにしました。現在は、タレント向けのカウンセリングなど、メンタルヘルスケアのサービスもご案内しています。
海外タレントについては、特に配信環境の確保が重要な課題です。来日して活動される時には、一般的なホテルではWi-Fiが弱く配信に支障をきたすため、配信機材を完備した環境を用意しています。また、興行ビザの取得支援も重要な業務となっています。
これらのサポートは、管理本部内のタレントサポートチームが担当しており、タレントマネジメント部と密に連携しています。タレントと直接やり取りすることは少ないものの、マネージャーを通じて様々なニーズに対応しています。
リスク管理の面では、配信内容の事前チェックや注意喚起、配信中の荒らし対策として専門チームによるコメント管理も実施しています。予期せぬインシデントが発生した際には、関係部署と連携した初動対応から対外コミュニケーションまで、段階的な危機管理プロセスを確立しています。
これらの取り組みは、課題に直面するたびに一つずつ解決策を積み重ねてきた結果です。タレントの方々が安心して活動に専念できる環境づくりを、今後もさらに強化していきます。

「根拠ある挑戦の実現へ」成長企業における組織変革の軌跡
―入社から現在まで、カバーの組織としての変化を見てこられたと思います。管理本部の立場から見て、特に印象的な変化や、その中での気づきについて教えていただけますか?
各部門の要望に柔軟に対応してきた一方で、会社の規模拡大に伴い、そうした対応が時として公平性を欠くリスクも出てきています。個別の融通を効かせることが他部署との不公平につながったり、予期せぬ事故のリスクを高めたりする可能性があります。これまでは臨機応変な対応で乗り切れてきた案件も、会社の規模が大きくなった今では、より慎重な判断が必要となっています。
当社では挑戦的な提案を歓迎する文化がありますが、近年は「根拠のある挑戦」という視点を重視するようになってきています。特に注目しているのは、提案の背景にある根拠の説明と、明確な責任体制の構築です。現場からの新しいアイデアを採用する土壌は今でも健在ですが、以前に比べて「誰が責任者で誰がプロジェクトオーナーか」という点を経営層でしっかりと確認し、意思決定する体制を整えています。
組織が成長する過程で必然的にお堅い組織になっていく面はありますが、それは会社全体の健全な運営のために必要な変化だと捉えています。柔軟性と公平性のバランスを取りながら、全社の成長を支える管理体制の構築を目指しています。その両立を図ることで、持続可能な成長を目指しています。

「全社最適」を考える機会が増えた、現在のカバー
―加藤さんは2023年に執行役員に就任しました。執行役員就任前と後ではどのような変化がありましたか?
執行役員への就任は、上場準備の一環として執行役員制度が導入されたタイミングでした。特に大きな変化を感じたのは、意思決定における視点です。本部長会議や役員会議など、経営層での議論を通じて、様々な部門からの要望や課題をキャッチアップする機会が増えました。一段上の目線での意思決定が求められる中で、マネジメント層としての責任も日々感じています。
特に意識の変化を感じるのは、「全社最適」を考える機会が増えたことです。制度設計やトラブル対応など、日常的な意思決定において、単に部署間の連携という視点を超えて、会社全体にとって何が最適なのかを考えるようになりました。
この変化を支えているのは、充実した会議体の存在だと思います。本部長会議に加え、経営会議などの場で他部署の動向や様々な意思決定案件に触れることで、会社全体の状況を常にキャッチアップできています。最初は形式的な役職という認識でしたが、執行役員という立場は通常の本部長とは異なる、より広い視野での意思決定を求められる役割だと実感しています。
―人事部長として組織文化の醸成のために行っている施策があれば教えてください。
当社の特徴として、真面目で優秀な人材が多いことが挙げられます。時にはその真面目さゆえに部門間での意見の相違や軋轢が生じることもあります。そのため、会社のバリューである「枠を超えて結集する」という理念を実践するための様々な施策を展開しています。
特に重視しているのは、他部署を慮る姿勢の醸成です。日常的なコミュニケーションを通じて、お互いの業務や課題への理解を深め、より良い協力関係を築いていけるよう、様々な仕掛けを継続的に行っています。
具体的な大規模施策というよりも、日常的なコミュニケーションの機会を数多く設けることを重視しています。例えば全社ミーティングでの各部署からの発表や、トレーディングカードゲームなどの趣味を通じた交流イベントなどを行っています。
―ホロカでの交流が!
人事部が主催していますが、初心者向けの講習会も実施し、デッキも用意するなど、誰でも気軽に参加できる環境を整えています。毎回10-20名ほどが参加する人気イベントとなっています。
また、14階にある大規模なリラクゼーションルームは、最大100人収容可能な憩いの場となっています。ここでは「TGIF(Thank God It’s Friday)」と称した社内パーティーを定期的に開催し、特に海外メンバーとの交流の場として機能しています。人事部主催のこれらのイベントは、1-2週間前から告知を行い、毎回100人程度が参加しており、社員の交流の場として定着しています。
現在、谷郷CEOと社員が直接対話できる「タウンホールミーティング」の定期的な開催も試みております。取締役やアドバイザーも交えた、より開かれたコミュニケーションの場として機能させる予定です。これらの取り組みを通じて、部門や国籍を超えた社員同士の交流を深め、より風通しの良い組織文化の醸成を目指しています。一度や二度のイベントではすぐに効果は表れませんが、こうした機会を継続的に提供することで、徐々に部門間の理解が深まり、自然な連携が生まれてきています。
―社員の育成や成長のために、制度や研修面ではどういった施策があるのでしょうか?
人材育成については、社員からの声を反映しながら、様々な施策を展開しています。特に研修制度は予算を拡充し、階層や役割に応じた多様なプログラムを提供しています。
マネージャー層向けには、コンプライアンス研修やマネジメントスキル向上のための複数のコンテンツを研修形式で実施しています。これは必須研修として位置付けていますが、部署別の有志研修も併せて実施し、現場のニーズに応じた柔軟な学びの機会を提供しています。
一般社員向けには、ロジカルシンキングやファシリテーションの研修を実施しています。特にメディア系からの転職者が多い当社の特徴を踏まえ、ビジネスマナー研修なども現場からの要望に応じて導入しました。
また、グローバル展開を進める中で、異文化理解研修にも力を入れています。外部講師を招いての研修後、社員同士での継続的な学び合いの場も設けています。社員の学びを支援するための学習補助金制度も設けており、個々人のスキルアップへの投資も積極的に行っています。その他にも有志による持株会の運営など、社員の長期的なキャリア形成支援にも取り組んでいます。
今後の課題としては、社員のキャリアパスのモデルケース作りがあります。急成長する企業ならではの多様なキャリアの可能性を、より明確に示していければと考えています。
「グローバルスタンダードを見据えて」エンターテインメント産業の健全な発展に向けて

―グローバル展開を加速させる中で、人事/法務知財・危機管理本部長として現在特に注力されている点を教えていただけますか?
クリエイティブ職については多くの優秀な人材に応募いただいていますが、今後はビジネス職やコーポレート部門の採用により一層注力していきたいと考えています。現在海外社員は日本語と英語の両方ができる人材が中心ですが、今後は英語のみの社員も増えていく見込みです。
人事部としては海外展開における組織づくりに注力しており、グローバル展開の実績を持つ他IT企業経営陣の方の知見にも助けていただきながら、体制構築を進めています。英語が得意ではない社員も多いため、英語の習得そのものを強制するのではなく、異文化理解にフォーカスしたアプローチを取っています。言葉の壁は翻訳チームのサポートで乗り越え、むしろ納期感やクオリティに対する考え方など、文化的な違いの理解に重点を置いています。
翻訳のセクションは社内資料の日英翻訳を担当するブリッジチーム、外部に発信するコンテンツの翻訳全般を担当とするローカライズチームに分かれています。どちらも多岐にわたる業務に関わっており、ブリッジチームは月に一度開催される全社ミーティングの同時通訳なども行いますし、ローカライズチームはアニメ「ホロぐら」や歌ってみた動画の多言語字幕の作業も担当しています。。こうした体制は新しく入ってきた方からこんな制度があるなんて、と喜ばれることも多く、今後も現場の声を聞きながらグローバルな組織として、異なる文化や価値観を持つメンバーが共に働きやすい環境づくりを目指しています。
―カバーを取り巻く環境に課題はありますか?また、その解決に向けた取り組みについて教えてください。
近年、エンターテインメント業界、特にアニメ分野に対するコンプライアンスの要求が急速に高まっています。これは単なる上場企業としての要請だけでなく、業界全体の構造的な変化を反映したものだと考えています。
実際、アニメ市場は10年で2倍に成長し、現在約3兆円規模に達しています。そのうち1.6兆円が日本国内、残りが海外市場という状況です。かつての「クールジャパン」的な文脈を超えて、世界的な主要産業として認識されるようになってきました。これまで業界の高い品質基準は、しばしばクリエイターたちの過度な負担の上に成り立っていた面がありました。しかし、2023年10月には国連の人権調査委員会がアニメ業界の労働環境について言及し、Netflixでの配信是非にまで議論が及ぶなど、国際的な注目を集めました。業界の発展を支えてきた従来の働き方は、グローバルスタンダードの観点から見直しを迫られています。
当社も下請法の指導を受けた経験から、この課題の重要性を痛感しています。クリエイターの方々にとっては、時として規制強化と捉えられかねない施策も必要になってきますが、これは業界全体の健全な発展のために必要な道だと考えています。
現在は、業務フローの改善や長時間労働の是正など、具体的な取り組みを進めています。特に構造的な長時間労働の問題については、経営企画室と連携しながら根本的な解決策を模索しています。また、他社との協業やメディアミックス案件を通じて、業界全体での連帯感も生まれつつあります。
カバーとしては、業界のリーディングカンパニーとして、単にコンプライアンス対応に留まらず、むしろ業界全体の健全な発展のための情報提供や取り組みを積極的に行っていきたいと考えています。日本のアニメやVTuber業界が世界に誇れるエンターテインメント産業として発展していくために着実に進めていく必要がありますし、タレントやクリエイターが持続可能な形で活躍できる環境づくりを強化していきます。
―現在の等身大のカバーを一言で表すとしたら、どんな言葉を選びますか?
「大人になりつつある会社」だと感じています。特にこの一年は、会社としての足元固めの重要性を強く実感する期間でした。
これは単純に保守的になるということではなく、カバーの持ついわゆる「少年の心」のような、新しいことへの挑戦や夢を追い求める姿勢は大切にしながらも、適切なリスク管理とのバランスを取ることが重要だと考えています。「大人になりすぎない」と同時に「子どもすぎない」という絶妙なバランスを目指しながら、クリエイターとともに持続可能な成長を目指していきたいと考えています。
エンターテインメントが日本の主要産業として認識される中で、私たちが創出するクリエイターエコノミーを確立することで、新たな可能性を切り拓く市場になり得ます。「日本発」でありながら、グローバルに通用するプラットフォームを提供することで、世界中のクリエイターに成功のチャンスを提供できる未来にワクワクしています。

ーありがとうございました!
役員インタビュー一覧
-

カバー取締役・植田修平が語る、世界のコンテンツ産業に不可欠な存在への挑戦
メディアミックス領域を管掌する取締役の植田修平さんに、VTuber市場の未来、海外展開戦略、そして業界が抱える本質的な課題について、詳しく伺いました。
記事を読む
-

「多彩な専門性で描くVTuberの未来」カバー林執行役員が語る、クリエイティブ制作本部が挑む表現革新への道のり
VTuberプロダクション領域を管掌する執行役員の林茂樹さんに、新しいエンターテインメントの創造に挑む制作現場について、詳しく伺いました。
記事を読む
-

「一過性のブームではない、10年先を見据えたビジネスへ」カバーCFOが描く、VTuber産業の可能性と展望
取締役CFOの金子陽亮さんに、カバーの成長戦略や将来展望について詳しく伺いました。
記事を読む
-

「日本発コンテンツを世界に届けたい」カバー前田執行役員が明かす、グローバル展開への挑戦と展望
MD・EC・物流領域を管掌する執行役員の前田大輔さんに、カバーのEC戦略と未来のビジョンについて詳しく伺いました。
記事を読む
-

「テクノロジーで世界を縮める」カバー取締役CTOが語る、VTuberからホロアースまでの技術革新と未来像
カバー創業期から技術戦略を牽引してきた福田一行CTOに、技術革新を続けるカバーの技術戦略や、新しいエンターテインメントの未来を創造する挑戦について、詳しく伺いました。
記事を読む
-

「日本発で世界に向けてエンターテイメントで突き抜ける」カバー谷郷社長が描く、VTuber文化とテクノロジーが拓く未来
代表取締役社長CEO 谷郷 元昭に、「第二創業期」を迎えたカバーが目指す「より大きなチャレンジ」の全容について迫りました。
記事を読む