
植田修平さんは、2023年にカバーの社外取締役、2025年4月から常勤取締役に就任し、現在はメディアミックス領域を管掌しています。
自身のキャリア最後のチャレンジとしてカバーへ本格参画を決めた理由、日本コンテンツ輸出20兆円時代の到来を見据えたVTuber市場の未来、海外展開戦略、そして業界が抱える本質的な課題について、詳しく伺いました。
取締役 植田 修平
新卒でイマジニア株式会社入社。2001年に株式会社ゲームポットを設立し、代表取締役に就任。FreeToPlayの先駆者としてオンラインゲーム黎明期を牽引し、IPOを果たす。その後、韓国大手ライブ配信AfreecaTV日本法人の代表をはじめ、数社の代表取締役を歴任。2025年より取締役に就任。一般社団法人日本オンラインゲーム協会共同代表理事。
「最後のチャレンジ」として常勤参画を決断。20兆円市場への確信
―植田さんは2023年に社外取締役として就任され、2025年4月から常勤取締役になられました。常勤として本格参画を決断された背景を教えてください。
元々谷郷CEOとはイマジニア社の先輩後輩の関係で、アドバイスをし合う関係が節目節目で続いていました。カバーの立ち上げ初期にもオフィスに行ったりと、事業の近況を聞いており、2023年から社外取締役として就任しました。当時から常勤取締役として事業を見て欲しいという話はあったのですが、就任の決定打となったのはVTuber市場が世界規模で成長できるポテンシャルを持っていると確信した部分が最も大きいですね。
世界で事業を大きく展開できるチャンスに、社外取締役としてガバナンスを指摘する立場でいた方がいいのか、それとも常勤取締役として自ら事業開発の指揮をとり海外展開をやりきる方がいいのかは非常に悩みました。自分の年齢を逆算すると、企業に100%以上コミットするというのは、おそらく最後だと思っています。そのチャンスに、これまでの経験や人脈を十分に生かせること、そして、世界に通用するような会社にすることへのワクワクを感じたので、常勤になることを決断しました。
―「世界規模で成長できるポテンシャル」は、具体的にどのような点から確信されたのでしょうか?
日本のコンテンツマーケットの輸出は年々増加し、2023年の輸出額は5兆円近くに増え、半導体産業や鉄鋼産業の輸出額を超え、自動車産業に次ぐ規模となりました。さらに2033年頃には、20兆円近く日本のコンテンツが海外に輸出されると予測されています(※1)。
特に近年、NetflixをはじめとしたOTTサービス(※2)の影響は非常に大きく、2025年には日本産コンテンツの占有率が北米でも29%近くのシェアを占める(※3)ほど伸びて、アニメやアニメルックのキャラクターの認知度が世界で上がっていることがわかります。
アニメルックなVTuberに対しての親近感が増えていくなか、VTuberが世界中のゲーム、アニメ、音楽のハブとなる未来も十分考えられます。世界中のアニメ、ゲーム、音楽ファンたちにVTuberをリーチさせていくことで、さらに世界規模のコンテンツとなっていけると思います。
※1:出典 経済産業省「エンタメ・クリエイティブ産業戦略 ~コンテンツ産業の海外売上高20兆円に向けた 5ヵ年アクションプラン~」
※2:OTTサービス(Over-the-Top media service:オーバー・ザ・トップ・サービス):インターネットを通じて直接提供されるメッセージや音声、動画などのコンテンツやメディアサービス
※3:出典 調査会社Ampere Analysis「Japan’s franchises take the lead on Netflix in North America as UK content declines」

台北ドーム史上最大記録を達成。世界で実感するファンの熱量
―メディアミックス領域という幅広い領域を管掌されていますが、今、特に力を入れている事業は何ですか?
一番注力しているのは、東アジアや北米を含めた海外展開ですね。特に東アジアのファンの熱量は非常に大きいです。この間、台湾で野球チーム「味全ドラゴンズ(Wei Chuan Dragons、繁体字中国語: 味全龍)」とのコラボレーションを実施しました。台北ドームという台湾で最も大きいスタジアムでコラボゲームを開催し、3日間通して入場者数・グッズ売上ともに、台北ドーム史上過去最大を記録しました。もちろん、野球を目当てに来ているお客さんが多いとは思いますが、ホロライブプロダクションとのコラボレーションによって、新しいファン層を野球場に呼び込むことができた側面もあると思います。
「子どもがホロライブのファンだから」という理由で現地の大手企業CEOも来場されていました。そういった熱気を海外でも感じると、さらにどんどん海外展開を仕掛けていって、ファン層を広げていきたいと切に思いますね。
―オンラインゲームの黎明期から長年エンタメ業界を牽引されてきた植田さんですが、その視点から見て、現在のVTuber市場はどのように映っていますか?
私がゲーム業界に入った1996年頃は、まだ「声優」という文化が根付いていませんでした。90年代後半くらいから、声優のアイドル化が進んできたり、コミケが市民権を得てきたりという流れがありました。アニメ作品のゲームも出るようになり、ゲームの中でも声優さんが重要になってきたり、キャラクター性をどう立たせるかが重要視されるようになってきたんです。
その流れの進化形がVTuberなのではないかという認識を私はしています。やっている方向性としては確かに新しいし、これから来る流れだなとは思っていましたが、本当に急激に大きくなったので驚いています。
―グローバル展開を進める上で、参考にされている事例や戦略はありますか?
海外展開において、ホロライブプロダクションが非常に恵まれているのは、すでに世界中にファンがいるということです。そこからマーケットをさらに拡大するにはどうすべきか、新たなファン層にどうリーチしていくかが、今やるべきことだと考えています。
特に重要だと考えているのは、SNSを活用した情報発信力とUGC(ユーザー生成コンテンツ※)を盛り上げる仕組みです。ホロライブプロダクションでは、二次創作の活用が大きな役割を果たしています。外部のクリエイターさんなど、様々な方が切り抜き動画をはじめとした様々な二次創作を作ってくださり、それが新しいファンとの最初の接点になっていることが多いです。
また、グローバル展開において、初期段階から多言語対応を意識したタレント構成なども参考になる事例だと思います。世界中の成功パターンから学びつつ、カバーならではの展開を追求していきたいですね。
※UGC:User Generated Content(ユーザー生成コンテンツ)の略称。サービスユーザーである一般消費者が発信するコンテンツを指します。(例:切り抜き動画、自作ゲームなど

―カバーという会社の最大の強みは何だと感じていますか?
ファンの熱量の高さが一番大きいと思います。ホロライブプロダクションは配信がベースとなっていますが、配信でファンになってくれた方の熱量を、音楽ライブに繋げて一つの大きな連鎖を起こして、そこでファン同士がまた集まって、同じコールをして……と、熱量が連鎖していき、大きな連帯感が醸成されていきます。どうやってそのファンの熱量を海外含めて連鎖させて大きくしていくか、を考えてるだけでもワクワクします。
TCG(トレーディングカードゲーム)の大会だと、会場の熱気はライブとは違って静かなのですが、初めて対戦する人同士が、「推しは誰ですか?」といった会話から始まり、ファン同士の交流が生まれています。様々なところでファン同士のタッチポイントが増えていけばいくほど、コミュニティが広がり、さらに面白い化学反応が生まれていきます。
ファンの熱量が高いからこそ、その期待に応える形で様々な事業展開が可能になります。TCGの領域には昨年から新しくチャレンジしていますし、来期からは本格的にゲーム事業も立ち上がってきます。ファンの皆さんの「こういう体験がしたい」という想いに応えていったり、これまでとは違う体験の場を提供していったりすることで、新しい楽しみ方が生まれていくんです。
私も長くエンタメ業界を見てきましたが、こうした熱量の高さは類を見ないですね。現地でファンの方に会い接することで、私自身非常に刺激を受けるので、ライブも行ける範囲で全て行きますし、カードゲームの大会やショップの視察もできる限り行っています。
―実際に現地に足を運ばれて、何か印象的なエピソードはありますか?
この夏に「hololive GAMERS fes. 超超超超ゲーマーズ2」というゲーム系のイベントをさいたまスーパーアリーナで開催したのですが、その直後に大阪出張があり、梅田の公式ショップ「hololive production official shop in Osaka Umeda」に立ち寄りました。
店長に「最近の売れ行きはどうですか?」と聞いたところ、埼玉でイベントがあった日に、そこに出演したタレントのグッズの売れ行きが急に伸びたと話していました。距離的には大阪と埼玉で、あまり連動しないだろうと思っていたのですが、ファン心理なのか、会場に行けなくても出演者のグッズを買うという消費行動が起きていたことに驚きました。
こうした事象から、イベント施策とグッズの連動性を考えると、ファンの行動のきっかけやストーリー付けは、もっとやっていけるのではないかと感じましたね。
VTuber市場の「次のステージ」へ。業界の進化と新たな挑戦
―長年エンタメ業界で経営に携わってこられた植田さんが考える、エンターテインメントを作る上で最も大切なことは何でしょうか?
エンタメを作る上で、最も大切なのは「人の心を動かすこと」です。データ分析だけを深掘りしても新しいものや感動を作るものは生まれてきません。前職でも「五感にどう訴えるか、どうやったら心に残るものにできるかをすごくこだわってやりなさい」とよく伝えていました。それらを実践した上で、できたものが面白いと思えるかどうかを大事にしています。
また、1つ1つの施策が点で終わらず線となり、ストーリーとして生きるものにすることも大切ですね。かつ、予定調和にならないようファンの期待を超える企画や施策であることも重要ですし、ファンは何を喜ぶのかという研究も必要です。そのためには様々な引き出しを持っていないといけないし、ファンの特性の理解も必要です。
これらを全てができているかどうかを会社として定量的に判断することは難しいですが、「こうしたことを大事にしている会社なんだ」という風土を作っていけば、会社として何が大事なのかということを考えられるクリエイターがどんどん社内で生まれてくると考えています。エンタメ企業を経営する上でも、そういう方たちが働きやすい環境を作ることを大事にしています。

―VTuber市場は急成長を遂げていますが、業界全体としての課題をどう見ていますか?
VTuber市場は第一期の勃興期がひと段落したと考えています。VTuberという文化が立ち上がった頃は本当にカオスの状態で、ファンコミュニティとのコミュニケーションの仕方やゲーム配信の許諾の取り方など、とにかく今できることをすぐやりながら、前に進んできたと思います。
しかし、市場が少しずつ成熟してきた今、段々とスマートな戦い方を考えていかなければいけません。今、そうした時期に差し掛かっている段階だと感じています。ただし、エンタメとしてファンの心を動かすためには、あまり大人になりすぎても良くない、というのが過去の経験則からも感じるところです。
また、VTuberという新しい職業をしているタレントさんたちの、10年後、20年後までを見据えた新しい道筋を作ることも今後の課題だと思っています。VTuberとして何十年も活動ができるようにサポートしていくのが我々だと思いますので、どうやって新しいステージや、キャリアパスを作っていくかというのは会社として非常に大事なことだと思います。例えば(あくまで想像しやすいようにする例ですが)、今までにないユニットを組んだり、新たな活動拠点を作ったり、もしくはプロデューサーとして参画してもらうなど、様々なやり方があると思います。そのロールモデルを、業界全体で作っていかなければならないと考えています。
―業界全体の課題に加えて、ホロライブプロダクション固有の課題についてはいかがでしょうか?
特に最近強く感じるのは、一般的な生活の中での時間の使い方が変化しているということです。例えば音楽でもNetflixのドラマでも、時間が長いと視聴されなくなってきており、どんどんインスタントなものが視聴されやすい時代になってきています。そのため、他のVTuberだけではなく、アイドルや歌手、アーティスト、アニメ、映画など、あらゆるコンテンツとの時間の奪い合いが起きています。
ホロライブプロダクションとしては、生配信を見て初めて、そのタレントの個性がわかり、本当のファンになっていくという側面が最も大きいので、生配信を見て欲しいのですが、今後長い時間の視聴が難しい世代が増えてくるのではないかと感じています。
Netflixを1.5倍速で見る、音楽もサビしか聞かない、TikTokで短い動画を次々と消費するといったカルチャーを持った若い世代がどんどん成長していく中で、どうホロライブプロダクションの興味を持ってもらい、ライブ配信を見てもらうかは重要です。
実際、ホロライブプロダクションのショート動画は非常に伸びていますし、そういう意味ではリーチはしやすくなっているのは確かです。そこからどう深いファンにしていくかというのが、これからの課題だと思います。

コンテンツ産業に不可欠な存在へ。5年後、10年後のビジョン
―今後カバーやホロライブプロダクションをどのように広げていきたいとお考えですか?5年後、10年後に実現したい姿を教えてください。
ホロライブプロダクションのタレントさん達が、コンテンツ産業において世界中に影響力を持つ存在として、輝ける舞台を提供することを目指しています。
具体的には、新しいゲームが発売される際のPRキャンペーンや、アニメのエンディング・オープニング楽曲など、様々なコンテンツのプロモーションにおいて「この作品を広めるなら、ホロライブのタレントに」と真っ先に声がかけていただけるような、不可欠な存在になれるよう、活躍できるフィールドを増やしていきたいと考えています。
また、タレントの影響力によって、世界中のファンにコンテンツの魅力を届けられる存在を目指していますし、5年後、10年後には、グローバルで様々なファンが熱狂している姿を思い描いています。今でもワールドツアーなどを行っていますが、ライブだけでなく、配信、ゲームの大会、トレーディングカードの大会など、世界各地のあらゆる場所でファンが熱狂している——そういった状態を実現したいですね。
―最後に、今のカバーを表すとどんな言葉になりますか?
「押さえつけられたマグマ」ですね。
会社としては大人になろうとしています。様々なガバナンスや予算管理、労務管理など、経営が高度化すればするほど、社内には押さえつけられている感覚が生まれていると思います。しかし、押さえつけられたままだと成長はありません。単なるつまらない会社になってしまいます。いかにその殻をバーンと破って、次のステージに行くか。どこかで爆発的なものをやらないといけないと思っています。
ー台北ドーム史上最大記録、埼玉と大阪の連動現象、TCG大会での交流など、植田取締役のお話から、世界各地で実感しているファンの熱量の高さと、その熱量を連鎖させていく想いが伝わってきました。
「押さえつけられたマグマ」を解放し、次のステージへ。世界のコンテンツ産業に不可欠な存在を目指す挑戦に、大きな期待が高まります。ありがとうございました!
役員インタビュー一覧
-
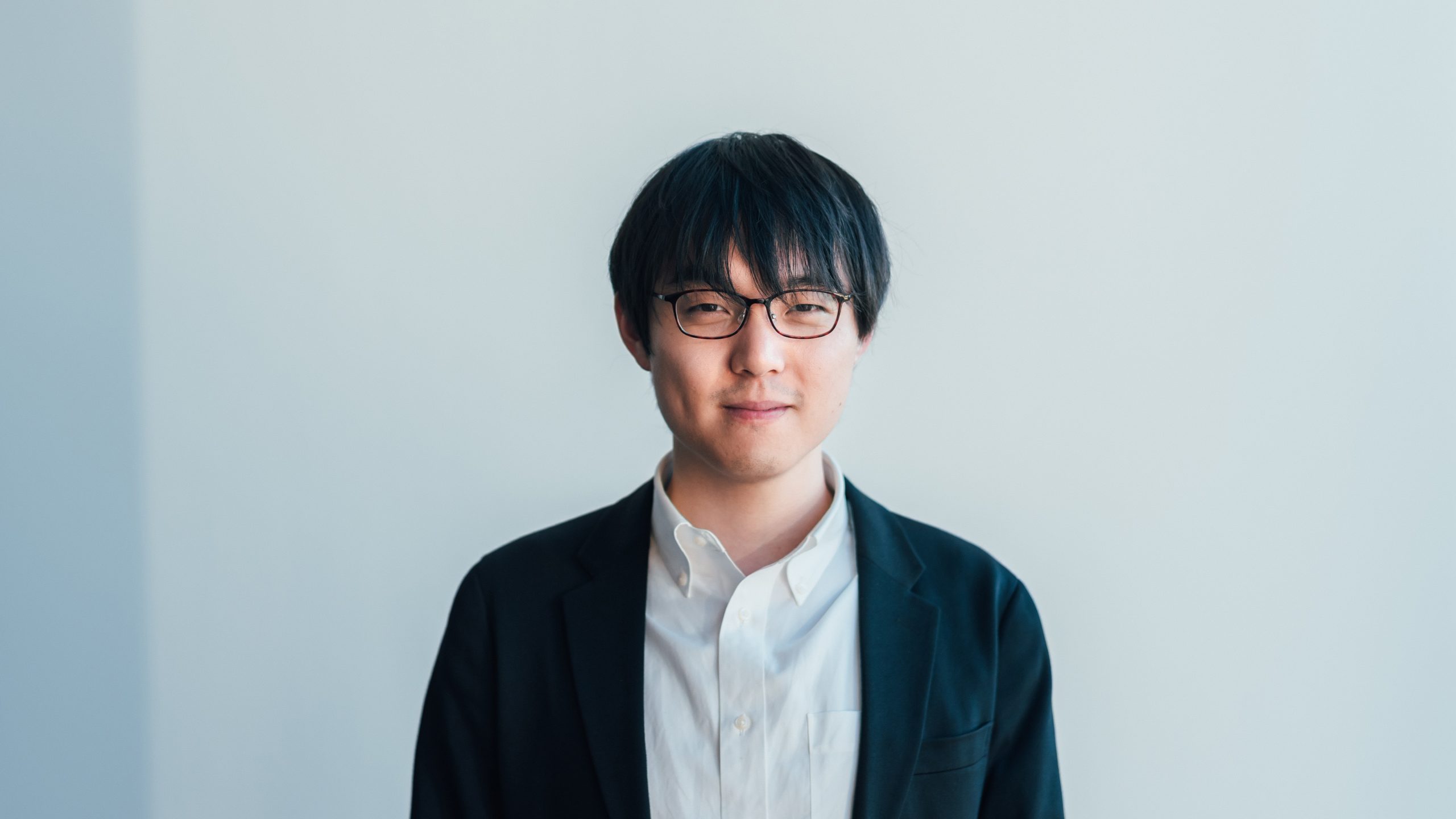
「クリエイターの夢を管理部門から支える」カバー執行役員が描く、挑戦を後押しする組織づくりへの挑戦
執行役員 人事/法務知財・危機管理本部長の加藤卓さんに持続可能な組織づくりを目指す取り組みについて、詳しく伺いました。
記事を読む
-

「多彩な専門性で描くVTuberの未来」カバー林執行役員が語る、クリエイティブ制作本部が挑む表現革新への道のり
VTuberプロダクション領域を管掌する執行役員の林茂樹さんに、新しいエンターテインメントの創造に挑む制作現場について、詳しく伺いました。
記事を読む
-

「一過性のブームではない、10年先を見据えたビジネスへ」カバーCFOが描く、VTuber産業の可能性と展望
取締役CFOの金子陽亮さんに、カバーの成長戦略や将来展望について詳しく伺いました。
記事を読む
-

「日本発コンテンツを世界に届けたい」カバー前田執行役員が明かす、グローバル展開への挑戦と展望
MD・EC・物流領域を管掌する執行役員の前田大輔さんに、カバーのEC戦略と未来のビジョンについて詳しく伺いました。
記事を読む
-

「テクノロジーで世界を縮める」カバー取締役CTOが語る、VTuberからホロアースまでの技術革新と未来像
カバー創業期から技術戦略を牽引してきた福田一行CTOに、技術革新を続けるカバーの技術戦略や、新しいエンターテインメントの未来を創造する挑戦について、詳しく伺いました。
記事を読む
-

「日本発で世界に向けてエンターテイメントで突き抜ける」カバー谷郷社長が描く、VTuber文化とテクノロジーが拓く未来
代表取締役社長CEO 谷郷 元昭に、「第二創業期」を迎えたカバーが目指す「より大きなチャレンジ」の全容について迫りました。
記事を読む






